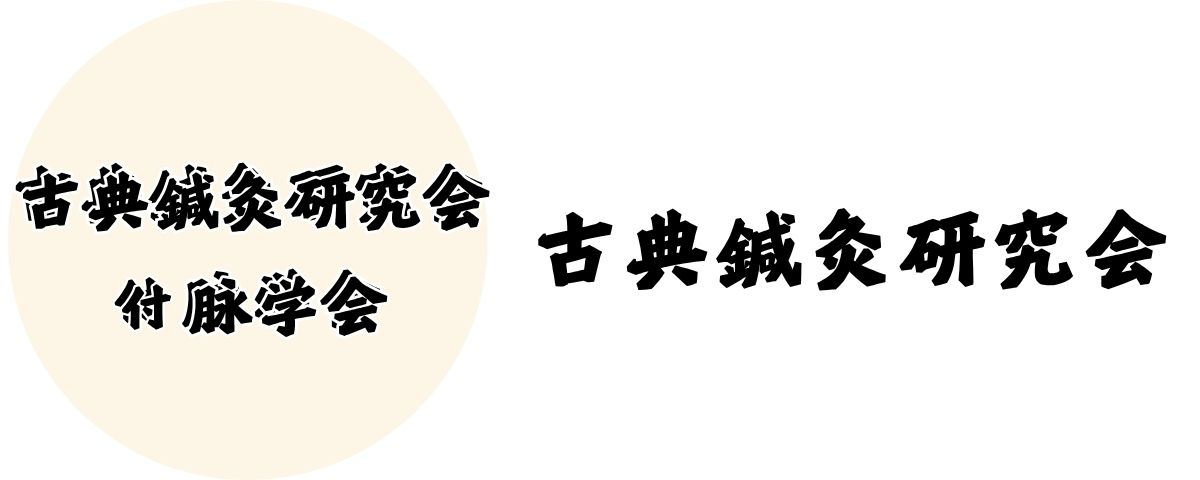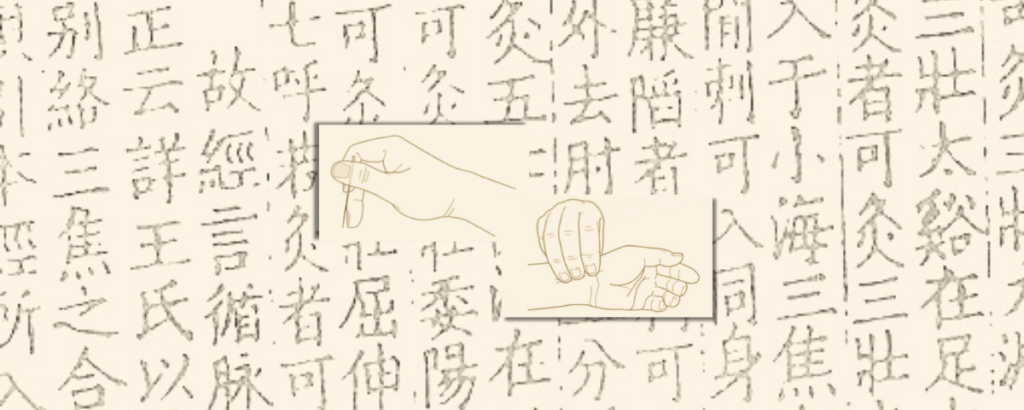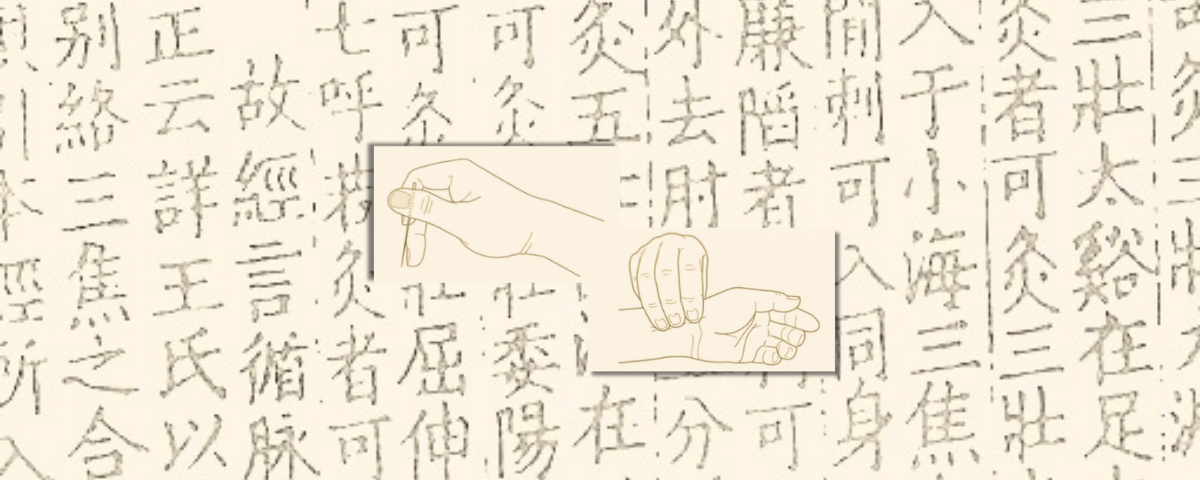古典鍼灸研究会(付脉学会)の理念
当会の理念は「鍼灸師の医学」を確立することである。
井上雅文が述べる「診断としては脉診のみ、治療手段としては鍼と灸だけである経絡治療だけが唯一の診断から治療へのシステムを持ち、創立から鍼灸師の医学であった。」「我々鍼灸師には湯液を含めた薬というものを使うことはできない立場にあり、西洋医のように近代的な診断検査機器装置を使うことはできないが、それゆえ、今我々は人間にとっては極めて自然で害のない医学の創造に参加しているのではないか」という考えや「鍼灸師にとっての進歩とは、今日治せなかったものが明日治せるように、今年治せなかったものが来年治せるようになるということです。」という言葉を胸に同氏が復活させた人迎気口診を用いた臨床や中国伝統医学文献の研究と臨床への応用の検証を中心に活動している。
沿革
日本の伝統医学として受け継がれてきた鍼灸に対し、啓蒙活動としての研究グループ設立の気運が高まり、
その志を同じくする人々が集い、昭和15年(1940年)9月2日、本間祥白を中心に「古典研究会」を発足させた。
当会は、『内経』をはじめとする古典文献を通じて、経穴・病証・臨床など古典的鍼灸術の基礎を学ぶことを目的としていた。
「鍼灸の本道は古典に帰るべし」と唱えた柳谷素霊を会長に、井上恵理を副会長に迎え、発会の場は両国・柳谷素霊主宰の日本高等鍼灸学院(覚王山灸療院2階)であった。
会員は十数名を数え、小野文恵、鈴木啓民、谷田啓道、早川満男らが名を連ねた。
柳谷素霊が多忙のため、同年12月以降は井上恵理が講義を代行。
柳谷は昭和31年(1956年)12月まで会長職にあり、秘法集公開や治験講義などを行った。
講義内容は、井上が前年まで岡部素道と共に行っていた『霊枢』の講読を基に構成され、
そのほか『鍼灸重宝記』『鍼灸遡洄集』『十四経発揮』『医方大成論』『癰疽神秘灸経』『難経』なども教材として用いられた。
当初は毎週月・金の早朝に実施され、後に夜間開催となる。時には終電を逃し、全員が泊まり込むこともあったという。
昭和17年(1942年)、本間祥白は『鍼灸補寫要穴之図』を自費出版。
後に医道の日本社より刊行されたこの図は、井上恵理の指導下で2年間にわたり患者ごとの本治法選穴を記録し、
膨大な経穴を五行分類で整理・集約した成果であった。
また本間と井上による『経絡経穴図鑑』もこの頃に制作され、その人体図は本間自身がモデルとなった。
以降、会員は『難経』研究に注力し、昭和19年(1944年)末には原稿草案を完成させるが、
翌昭和20年(1945年)3月の東京大空襲で焼失。
これが後年の『難経の研究』(昭和38年、医道の日本社刊)へと結実するが、本間は刊行を見ずして他界した。
昭和19年3月、本間祥白は『東医宝鑑』など江戸期医書を基に『鍼灸病証学』を出版。
以後、病証学研究は当会の伝統的課題として継承される。
同年12月の忘年会は戦火下の灯火管制の中で開かれたが、その後、戦災・応召・疎開などにより約2年間活動を休止。
昭和21年(1946年)9月、足立区末広町の真田俊次宅にて再発足。
井上恵理の研究指導のもと、谷田啓道・小野文恵・真田俊次・橋本三郎・根本憲四らが参加した。
昭和23年(1948年)12月20日、井上恵理は台東区入谷に「施無畏堂鍼灸療院」を開設し、これが新たな研究会場となる。
同年11月19日には戦後初の長期講習会(第2回、1年間)が開催され、以後、当会の会員資格は長期講習会修了者に与えられる慣例となった。
講習会は概ね3〜5年ごとに開かれ、令和3年(2021年)までに第21回を数える。
昭和31年(1956年)12月、柳谷素霊の後を継ぎ、井上恵理が第2代会長に就任。
当会では新年会は行わず、毎年の忘年会が恒例行事となる。
柳谷素霊は亡くなるまで出席し、従容迫らぬ姿で会員に慕われた。
石野信安、竹山晋一郎、戸部宗七郎らが招かれることも通例であった。
昭和34年(1959年)より、医道の日本社主催「経絡治療夏期大学」を後援(第11回=昭和44年まで)。
昭和37年(1962年)8月、副会長・本間祥白逝去。
翌昭和38年(1963年)4月、経穴特別研究会(木曜会)発足。
昭和39年(1964年)12月、名称を「古典鍼灸研究会」と改める。
昭和42年(1967年)5月、第2代会長・井上恵理逝去。
同年7月、小野文恵が第3代会長に就任し、『鍼灸重宝記綱目』の講義を通して後進の育成に尽力した。
昭和48年(1973年)12月、小野文恵は東方会会長専念のため会長職を譲り、井上雅文が第4代会長に就任。
その間、多くの古典籍の復刻が進められ、その中心には大野健司の尽力があった。
昭和55年(1980年)7月、井上雅文は六部定位脉診に加え、『脉経』に記される人迎気口診を再構築し「井上式脉状診」を提唱。
『脉状診の研究』を著した。
昭和57年(1982年)、井上雅文の提案と会員16名の努力により、鍼灸界初の『八十一難経』一字索引を約8か月かけて完成。
戦後研究の一つの到達点として、東洋医学研究会(現オリエント出版社)より『難経古注集成』とともに刊行された。
昭和60年(1985年)頃より、医古文読解のための勉学が例会で始まり、他の古典派に先駆けて実践された。
平成6年(1994年)4月には脉学会と合併し、「古典鍼灸研究会(付脉学会)」が正式名称となる。
平成7年(1995年)11月23日、ホテルオークラにて創立55周年記念講演・祝賀会を開催。
石田秀実・丹沢章八両氏の記念講演をはじめ、岡田明佑・岡部素明・後藤修司・戸部宗七郎・戸部雄一郎諸氏を迎え盛会となった。
平成12年(2000年)11月23日、赤坂プリンスホテルにて創立60周年記念講演・祝賀会を開催し、石田秀実氏が講演。
平成17年(2005年)、昭和56年から続く木曜会(経穴部位研究)の成果として、『経穴考按』を皆川寛の主導、高橋和夫の協力により刊行。
平成19年(2007年)10月14日、井上雅文会長逝去。
同年12月、樋口陽一が第5代会長に就任。
平成23年(2011年)8月、『脉状診の研究』に基づく井上式脉状診の臨床的講義録『脉から見える世界』を発刊。
令和2年(2020年)12月、中村耕三が第6代会長に就任。
現在も臨床を主体に、井上式脉状診を発展させつつ、中国伝統医学の研鑽と鍼灸師の学術的向上に努めている。